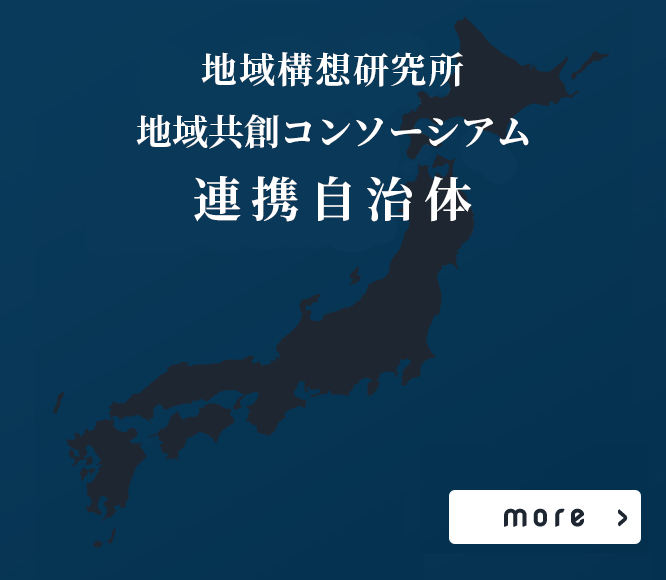今夏も新型コロナウイルスの感染者が増加しているというニュースを目にしましたが、2020年から数年間続いた緊張感は遠い昔のように思われます。しかし、あの当時の感染拡大は私たちの行動を制限し、生活上に外的変化を与えただけでなく、内面の価値観や人生観にも大きな変化を生じさせたことは、多くの人に共通する経験ではないでしょうか。
価値観や人生観への影響に地域差はあるのか?
実際に価値観や人生観にどんな変化があったのか。さらに、同じ日本国内であっても、地域によって受け止め方の違いはあったのか。この点に着目して、筆者と髙瀨顕功先生(大正大学公共政策学科 准教授)は2022年に秋田県と東京都在住のそれぞれ20名(どちらも一般10名、僧侶10名)、計40名にインタビュー調査を実施しました。(詳細は「新型コロナウイルスによる価値観・死生観の変化 —秋田と東京の比較から—」参照)
この2地域を選んだ理由は、秋田県と東京都の人口動態・感染状況ならびに宗教への結びつき(寺檀関係)が対照的だったためです。秋田県は人口の一極集中が指摘される東京都に対して、国勢調査に基づく人口減少率が5回連続で全国最大という状況にあります(2024年1月1日時点で東京都人口13,911,902人、秋田県人口924,620人)。新型コロナウイルスが5類感染症に移行した2023年5月8日時点での秋田県の感染者累計203,791人、死亡者数604人、一方、東京都は、感染者累計4,386,904人、死亡者数8,124人でした。また、秋田県は比較的寺檀関係が密であり、葬送儀礼も伝統的な方法が守られている地域であるのに対して東京都は葬送儀礼の簡素化・小規模化が顕著で寺檀関係も希薄と言われる地域でもあります。
秋田・東京の共通点
まず、2地域に共通して見られた変化は「人間関係」、「生活の見直し」、「健康への意識」、「死生観」でした。
①人間関係:対面でのコミュニケーションの減少という外的変化はもちろんのこと、会うべき人=大事な人というように優先順位が明確になり、人間関係を整理できたというポジティブな意見が目立ちました。
②生活の見直し:自粛生活のなかでこれまでの家族関係を再考したり、ワークライフバランスをコロナ前に比べてプライベートに重きを置くようになったり、生活の外的変化にともない、価値観に変化が生じている様子がうかがえました。
③健康への意識:感染対策や自粛生活による運動不足対策からの身体的な健康志向のほかに、精神的健康の低下に言及する回答も共通して見られました。
④死生観:死をより身近に感じるようになったり、面会禁止のなかで死んでいくことはどういうことなのかと考えたり、死について考えるようなったという意見が見られました。
秋田・東京の相違点
「新型コロナウイルスへの恐怖感」と「葬儀・供養に対する考え方」の2点において、明確な相違がみられました。
①新型コロナウイルスへの恐怖感
秋田県では、初期は感染者が少なかった分、「かかったら村八分になる」という恐怖感が強くありました。流動性が高く、人口の多い東京と違い、秋田は感染者が特定されるような環境であり、そのため噂が広がることを懸念する声もありました。
一方、東京都は感染者数が多く、新型コロナウイルスに対する恐怖はあったが、身近に感染者がいることが当たり前になっていくなかで、「どこにでもコロナ患者がいる」という認識が広まり、特にオミクロン株以降は「かかるのは仕方がない」と恐怖感が薄まっていったようです。
②葬儀・供養に対する考え方
秋田県では、もともと葬儀をしっかりやる文化でしたが、コロナ禍で急速に簡素化・小規模化が進んでいきました。僧侶からは「本当にこれでいいのか」という戸惑い・疑問を持つ声が多く、一般からは「これで十分」「仕方がない」と変化を許容する意見も見られました。
東京都は新型コロナウイルス感染拡大より前から「家族葬」や「火葬のみ」の形式をとる葬儀が一般化していたため、大きな変化を感じる人はいませんでした。
「感染状況」×「地域風土」
秋田と東京の2地点の相違は、感染状況と地域風土が掛け合わさった結果と言えるのではないでしょうか。ある種のムラ社会が残る秋田では、感染者数が少ないが故に感染者が特定されやすい環境にあり、そのため住民は自身の感染に対して強い恐怖心を抱いていました。一方で人口密集で近隣の人間関係がドライな東京では、いちいち感染者を特定する意識も弱かったのでしょう。葬儀・供養も、東京は簡素化・小規模化への違和感は少なく、近隣住民の多数の参列が当たり前だった秋田では、コロナ対策を口実とした簡素化・小規模化に戸惑いを覚える人も多かったようです。同一国内であっても、地域によりコロナ禍の受け止めは異なる側面があり、コロナの内的影響を把握するためには多角的な視点が必要になるでしょう。