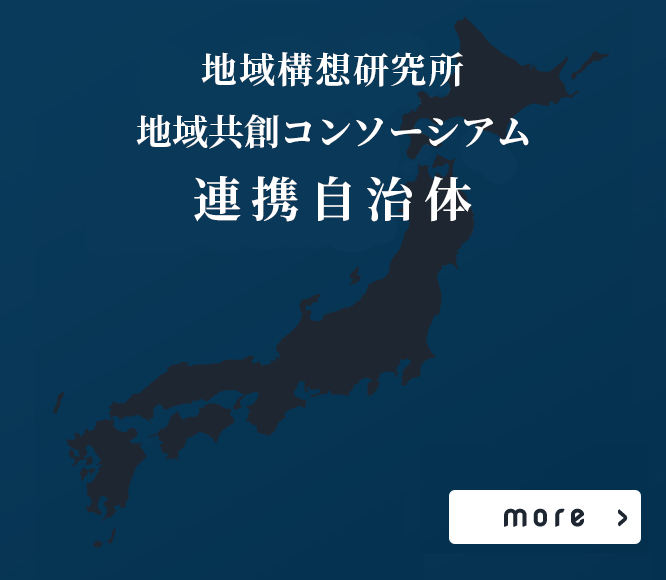防災・減災ワークショップ
関東大震災から100年を迎える今年、地域構想研究所では、来るべき大地震(南海トラフ地震、首都直下地震など)や、激甚化・頻発化している風水害、避難行動要支援者対策などについて、自治体の壁を越えて情報交換、意見交換するワークショップを4回シリーズで開催いたします。
第1回 令和5年7月4日(火)「いざという時の罹災証明書発行」終了
続編の開催が決定しました!
第1回 続編 令和5年11月7日(火)「いざという時の罹災証明発行」終了
お申し込みはコチラ⇒https://forms.gle/wNTR2a1GHm2Hdk286
第2回 令和5年8月24日(火)持続的な地域構築のための「地域共創流域治水」終了
⇒詳細・お申し込みはコチラ↓
第3回 令和5年11月30日(木)「順調ですか?個別避難計画作成」 終了
⇒詳細・お申し込みはコチラ ↓
https://forms.gle/dtK2GY9JeRYHhzvg6
第4回令和6年3月26日(火)「令和6年能登半島地震~石川県で進む新たな取り組み!」
⇒詳細・お申込みはコチラ ↓
本ワークショップは定員に達したため、申し込みを締め切らせていただきました。多数のお申込みありがとうございました。
地域政策構想技術リスキリング集中プログラム
本プログラムは、<自治体経営から地域経営への転換と地域再生DX>をテーマにオンデマンド配信とリアルタイムの政策構想ディスカッションを組み合わせ、自治体の議員や職員研修などへ、これからの地域構想の材料を提供します。
地域再生DXの推進に伴うリスキリングの機会として、ぜひご参加ください。
*6月1日からオンデマンド講座スタート
*受講生、受講自治体募集中!
⇒「地域政策構想技術リスキリング集中プログラム」TOPページへ