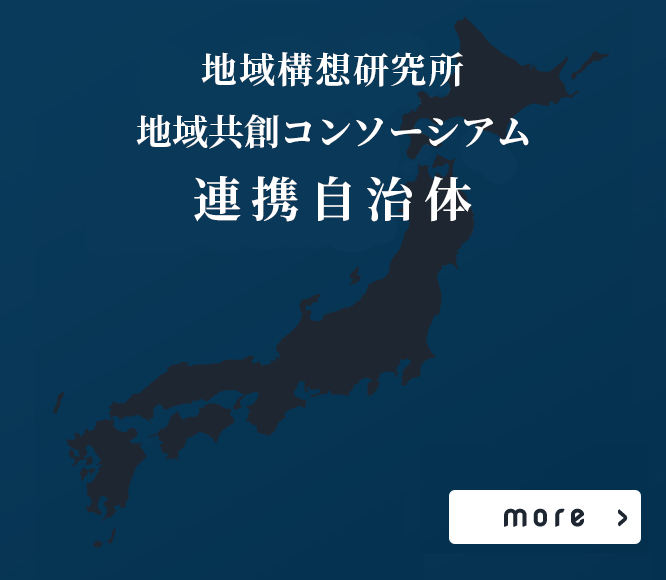髙瀨 顕功
-
読経で健康!プログラムin大正大学
BSR推進センターでは、昨年10月から12月にかけ、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所(以下、東京都健康長寿医療センター)および大正大学綜合仏教研…
-
第5回「寺院における新型コロナウイルスによる影響とその対応に関する調査」について
【第5回 調査回答フォーム:所要時間10~15分】 2020年初頭の新型コロナウイルスの感染拡大から間もなく丸4年が経とうとしております。今年5…
-
超高齢社会における寺院・僧侶の可能性
これまで、BSR推進センターでは、挑戦的萌芽研究「多死社会における仏教者の社会的責任」(課題番号:15K12814)(2015年度-17年度)、挑戦的開拓研究「…
-
「超高齢社会における寺院・僧侶の可能性」報告書
超高齢社会・多死社会を迎えるわが国で、伝統仏教(僧侶・寺院)が地域の社会資源として、高齢者ケアに寄与する大きな役割を果たしうるのではないかという仮説のもと、科学…
-
第4回「寺院における新型コロナウイルスによる影響とその対応に関する調査」結果報告
このたびは弊センターによる第4回「寺院における新型コロナウイルスによる影響とその対応に関する調査」にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。遅くなりま…
-
第4回「寺院における新型コロナウイルスによる影響とその対応に関する調査」について
2020年初頭の新型コロナウイルスの感染拡大から間もなく丸3年が経とうとしております。社会生活に制約、制限があるなかで、皆様の法務・寺院運営にも様々な影響が生じ…
-
【BSR】『コロナ禍における支援現場の対応―川崎ネット縁活動報告書―』が刊行されました!
本活動は、社会技術研究開発センター(RISTEX)「都市における援助希求の多様性に対応する公私連携ケアモデルの研究開発」(平成28年度~平成31年度)の成果を社…
-
仏様が出向いて新たな縁づくり
今こそ仏教を BSR推進センターでは、コロナ禍の中、これまで3回にわたるオンラインアンケート「「寺院における新型コロナウイルスによる影響とその対応に関する調査…
-
オンライン坐禅会でご縁を広げる
コロナ禍がもたらした影響 BSR推進センターでは、コロナ禍の中、これまで3回にわたるオンラインアンケート「「寺院における新型コロナウイルスによる影響とその対応…
-
第3回「寺院における新型コロナウイルスによる影響とその対応に関する調査」結果報告
このたびは弊センターによる第3回「寺院における新型コロナウイルスによる影響とその対応に関する調査」にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。いただきま…