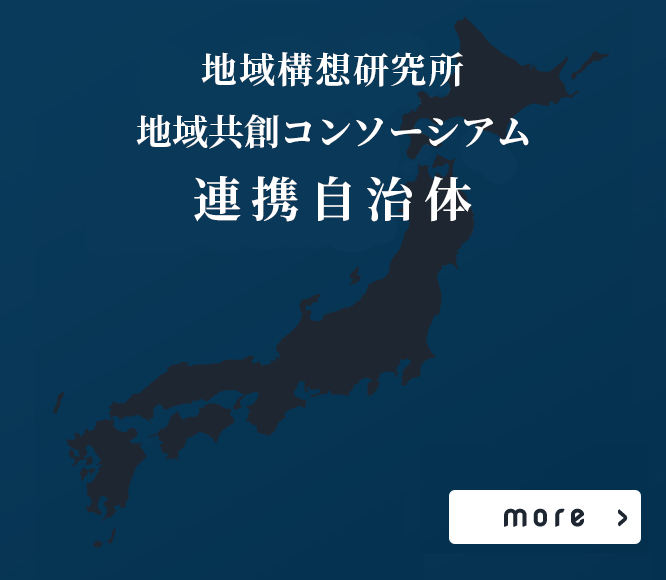コロナ禍が過ぎて、日本国内の観光客や海外からのインバウンド客が急激に増え、ニュースや色々な報道番組でオーバーツーリズムの言葉がよく聞かれるようになってきました。特に京都(嵐山、清水寺等著名な寺社仏閣)や東京(浅草や築地等)、富士山周辺では訪問者が過剰に集中しすぎることで、地域社会・自然環境・観光体験の質などに悪影響を及ぼす現象が起きています。
その一方で、人口減少が進み消滅可能性自治体と言われている地域では、人口を増加させる為の施策や交流人口や関係人口を増やす施策として国内観光客やインバウンド客の誘客を重点目標に掲げている地域が多いようです。
インバウンドの成功例を考えるとき、まず思い浮かぶのは東京都や京都市ですが、これらの都市は日本を代表する観光都市であり、近くに国際空港が控えており、特別の条件を備えています。
ですから、ここでは地方で成功している小布施町1)やニセコ町2)3)を例に挙げ、課題地域と比較することで、成功の要因を考えていきたいと思います。比較にあたっては、観光庁が推進しているインバウンドの重要要素を以下に項目として挙げ、これを中心に考えていくことにします。
小布施町では故市村良三町長のリーダーシップにより、“歩きたくなる道づくり”で回遊性の高いまちづくりを重視し、街全体が美術館の景観を実現しています。
ニセコ町は日本で初めてカタカナ名を正式に採用した自治体であり、現在世界的リゾートの“ニセコ”に育った地域です。
どちらもイノベーターのリーダーの元に成功を収めブランド化された地域であり、観光コンサルタントを長く経験した筆者にとっては、過去に関わった経験がある、非常に思い入れ深い地域です。これから観光に取り組む地域や成果が見通せない地域の参考になれば、と考えています。
1.明確なブランドと魅力の見せ方
小布施町は「北斎」「栗」「和文化体験」などで外国人に認知されています。
ニセコ町は「世界有数のパウダースノー」「富裕層向けリゾート」として明確なターゲットに絞ったブランディングを実行しています。
一方、誘客に取り組んでいる多くの地域は「どこでもある観光地」になってしまいがちで、外国人にとってのその地域に行く明確な「目的」が見えにくくなっています。
多くの観光地は、地域の観光の固定概念から脱皮できずにいます。未だに同じような観光スタイルを続けているように見えるのです。例えば、東日本大震災の被災地である三陸地域では、震災復興や豊かな海鮮を観光資源としていますが、近隣の町も全く同じような観光スタイルになっているように見えます。
同じような観光資源でも、この地域はここが他の地域と大きく違う、と言い切るようなインパクトのあるセンテンスが必要だと思います。
2.多言語対応・受入れ体制
小布施町の駅にある観光協会の総合案内所では英語対応スタッフが常駐し、訪日観光客にとって分かりやすく、安心して滞在できる町づくりを進めています。
ニセコ町では英語表記が多く、英語スタッフが常駐し、外国人でもストレスなく滞在でき、外国人経営の施設も多くあります。
両地域では多言語での案内体制やデジタル・AIの活用を通じて、持続可能で質の高い観光コミュニケーションの実現を目指しています。一方、まだ対応が遅れている地域では案内板やメニューが日本語のみであったり、外国語対応できる人材が不足している為、「来ても楽しめない」環境になっていることが多いのです。

小布施駅前の総合観光案内(多言語対応)

ニセコ町の看板
ニセコ町役場には、マレーシア・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・中国出身の国際交流員が計5名在籍し、地域の多文化共生推進を担っています。小布施町でもニセコ町でも国際人材の育成・配置、 多言語Web整備、 相談窓口の運営など、多様な施策を連携させながら、外国人住民や観光客への利便性を高めています。これにより、リピーターの誘致や定住につながる信頼できる環境が整備され、「外国人に選ばれる地域」へ着実に進化しつつあります。
その地域の多言語対応や受け入れ体制は、ゲートウェイ(駅、空港等)や街中にどれだけ外国人に分かりやすく案内されているかで判断できます。

ニセコ町の風景(ほとんどが外国人観光客)
3. SNS・口コミによる発信力
小布施町やニセコ町はInstagramやYouTubeなどでも頻繁に紹介され、「行きたくなる場所」としての印象形成に成功しています。ニセコ町の Instagram/YouTube は、季節ごとの自然美やアクティビティを演出し、リゾートとしての魅力をグローバルに発信しているのが特徴です。
(ニセコ町公式アカウント https://www.town.niseko.lg.jp/social_media/)
小布施町は、美術館・まち歩き・食文化など落ち着いた和空間と日常が織りなす魅力を学びや旅のスタイルで発信しており、外国人旅行者にも人気が非常に高い地域になっています。
(小布施文化観光協会 「小布施日和」 https://www.obusekanko.jp/)
一方、多くの地域では魅力があっても発信が弱く、認知されないまま埋もれてしまうケースが多いようです。また、そもそもSNS等の発信をしていない地域もいくつもあります。これでは外国人はもとより、日本の観光客でも興味が持てなくなります。
観光地公式 SNS は、視覚的に「行きたくなる魅力」を伝える重要な施策です。投稿内容 や更新頻度を今後の施策にも盛り込んで行く必要があります。
このように上記3項目を軸に見ていくと、インバウンドに関する交流人口の拡大を成功させるには、「継続的な関与の仕組み」「地域内外の協働」「地域住民の理解と積極性」がカギのようです。一過性の観光誘致に終始せず、「何度も来てもらえる理由」「地域との接点づくり」が大事、ということでしょうか。インバウンドのみならず、国内観光客にもリピーターで来てもらえるような魅力付けが必要なのだと思います。
参考資料
1)川向正人(2010)「小布施まちづくりの奇跡」新潮社
2)石田祐輔(2021)「ニセコ町観光の諸相と観光振興ビジョン策定に向けた展望」北海道大学
3)北海道ニセコにおける観光地域研究 」小樽商科大学『商学討求』第67巻 第1号