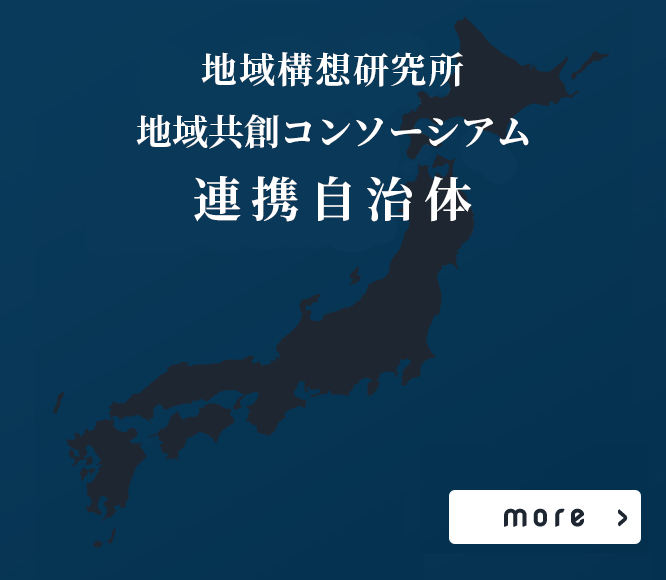「地域創生」と聞くと、どのような場所を思い浮かべるでしょうか。
地方の過疎地域や農村部の活性化が思い浮かぶ方も多いかもしれません。しかし、東京のような都市部にも、実は「地域創生」が必要とされる場所が存在しています。今回ご紹介するのは、東京都世田谷区の「下北沢再開発プロジェクト」。都市再開発のなかでも、住民と企業、行政が対話を重ねて進められた先進的な事例です。
プロジェクトの背景:開かずの踏切と木造密集地の課題
下北沢は、戦後の闇市の面影があり、坂道や細い路地が多く、独自の文化が色濃く残るエリアです。若者だけではなく近年では外国人観光客にも人気となり賑わいをみせています。
その一方で、「開かずの踏切」による交通問題や、災害時のリスクが高い木造密集地域といった都市課題を長年抱えてきました。小田急線と京王井の頭線という二つの鉄道が街を分断し、住民にとっては早期に解決を望む課題も存在していました。
2004年に始まった小田急線の地下化事業(東北沢駅~世田谷代田駅)は、これらの課題を解決する大きな転機となりました。地上から線路が消えることで生まれた全長1.7kmの跡地。この貴重な都市空間をどう活用するかが、「下北沢再開発プロジェクト」の出発点です。
対話から始まる街づくり
都市再開発においては、開発企業と行政が主導する形が多く見られますが、このプロジェクトでは早い段階から地域住民の参加が重視されました。
区が主催する「北沢デザイン会議」、住民主体の「シモキタリングまちづくり会議」といった協議体が立ち上がり、誰でも参加できる形で街づくりの方向性が話し合われました。ここで大切にされたのが、「つなぐ」というキーワードです。
•四季とやさしさが人をつなぐ
•街の記憶や風景が地域をつなぐ
•みんなで創り、時を超えて心をつなぐ
これら3つの“つなぐ”コンセプトを軸に、デザインコードや整備方針が住民との対話を通じて練られていきました。
企業が地域に歩み寄るという姿勢
特筆すべきは、小田急電鉄の姿勢の変化です。
当初、開発を主導する立場であったため、地域の反発を懸念して住民会議への参加をためらっていた同社。しかし、2017年にプロジェクトリーダーが交代すると、同社も地域との対話の場に加わるようになります。
結果的に、住民たちは小田急電鉄を“仲間”として迎え入れました。会社としても、街の歴史や文化、住民の声に真摯に耳を傾けることを通じて、“ただの開発”ではなく“地域とともにある開発”へと歩みを進めていったのです。
実践される「協働」のかたち
このプロジェクトでは、計画策定だけでなく、整備・運営にも地域の力が活かされています。
世田谷代田駅前に設けられた「代田富士356広場」では、住民自らが花壇の植栽やイベント運営を行い、空間を“育てる”主体になっています。また、園藝や空き地活用などをテーマにした住民グループが次々と誕生し、街の中に新しいコミュニティの芽が育っているのです。

世田谷代田駅前のダイダラボッチの足跡

シモキタ雨庭広場から見た遊歩道

歩道にデザインされた線路のイメージ
共通の目的は、対話の中から生まれる
この事例から学べる最大の教訓は、「対話と共通目的の形成」が再開発を成功に導く鍵であるという点です。
行政、企業、住民。立場も目的も異なる人たちが集まる場で、一つの方向を見出すことは簡単ではありません。しかし、対話を続け、信頼関係を育てていくことで、分断はつながりに変わります。
“都市の再開発”は、もはやハード整備だけでは語れません。地域の声を取り入れ、共に作り、共に育てていく姿勢こそが、持続可能な街づくりの鍵となるのです。