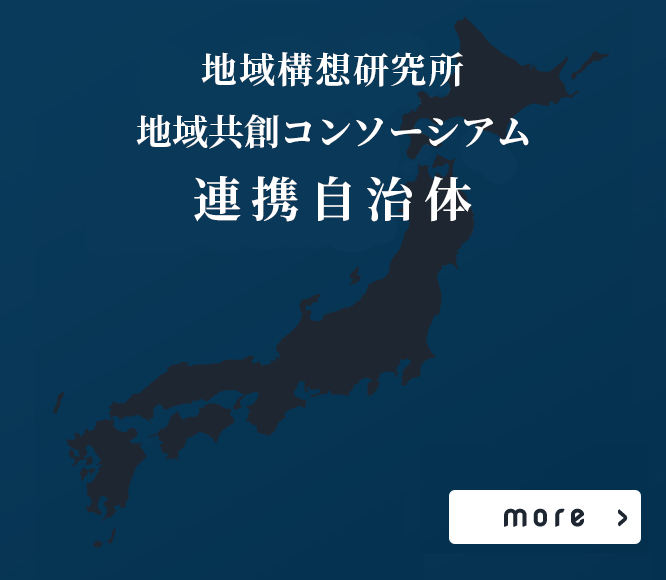本格的な夏山シーズンが到来しました。先日は北アルプスの最奥部にある三俣山荘と環境省の共催による登山道補修の人材養成研修にオブザーバーとして道直しの見学、体験の機会を得ました。登山道は山歩きには不可欠な存在であり皆様も歩いたことがあるかと思いますが、道直しを体験した方は限られると思います。今回は現場での体験談をご紹介しつつ今後の登山道のあり方について少々考えてみたいと思います。
三俣山荘は富山県、長野県、岐阜県の県境付近にあり、中部山岳国立公園内の黒部川の源流部に位置します。人工物が殆どなく利用者も比較的少ないことから原生的な自然環境を楽しむことができ、チングルマやキヌガサソウなどの高山植物や国の特別天然記念物でもあるライチョウにも今回出会うことができました。

チングルマ

キヌガサソウ
それでもシーズン中の登山道利用者数は約3万人と、数だけ見ると少なからぬ人数であり踏圧による登山道へのネガティブなインパクトは無視できないものがあります。具体的には森林限界を越えて元々草原であったところに人が歩くことで裸地となり、雨でぬかるむことで道が複線化し、更なる踏圧が続くと道と道の間の島状に広がっていた植生も徐々に土壌が崩壊、流出して裸地化し、道幅が広がっていくプロセスを辿ります。これは踏圧により道が裸地化して更に繰り返し踏みつけられることで土が硬くなり、降雨時に水の勢いが強まることで両脇の土が徐々にえぐられていくことによるものです。
今回の研修ではまず午前中に自然観察に行き、山荘のスタッフの方々の解説をいただきながら上記のような状況を確認しました。道直しはまずしっかりと現場を観ることから始まります。降雨時の登山道は川のようなものだとも言われますが施工前に水の流れを想像することも大切です。水の道をしっかりと把握し、登山道の外へ排水し登山道の侵食を防ぐことが重要となります。
今回、現場で意識を新たにしたのはストックによる悪影響です。ストックは登山する際には大変便利なもので岩や石の上で使う分には問題はありませんが、植物の生えている部分を繰り返し突き刺してしまうと植物は枯れてしまい裸地化し、更に繰り返し突き刺すことで土砂の崩壊や流亡を促進してしまいます。一つ一つの行為は小さなものかもしれませんがこれが繰り返されることで、登山道の荒廃という悪循環に繋がります。

ストック跡

ストックによる植生の裸地化の進行
今回、特に現場で学んだのはストックを一本持ちとするか二本持ちとするかによって登山道への悪影響に差があるということです。一本持ちの場合は自身の前にストックをつくことが多いのに対し二本持ちの場合は自身の両脇にストックをつくことで土砂崩壊に繋がりやすいことが挙げられます。現に私達の自然観察中にも二本持ちで登山道の両脇にストックをついている利用者を見かけましたし、ストックの跡や植生が無くなってしまった様子も確認されました。
現在、各地でストックにはキャップを付けましょうという普及啓発が行われていますが、ストックは登山道の両脇につかないことを徹底し、できれば二本持ちよりは一本持ちの推奨なども検討対象となると思います。山を歩かれる方々には豊かな自然や登山道を守るためにこれらの点を是非お心掛けいただけますと幸いです。
午後の研修では実際に少し荒れ始めている登山道の道直しを体験しました。
ご指導いただく山荘のスタッフ1人につきボランティア2人の各班3名体制で3班に分かれて作業開始です。
まず施工対象区間の不安定な石や土を取り除くところから始まります。その後に近くの沢付近から60、70キログラムはありそうな大きな石を背負子で山荘のスタッフさん達が担いできます。私のような素人で体力のない者にはとても無理な作業であり、私としては驚きの眼差しで眺めるしかありません。石の転がし方、載せ方、運び方にも様々なコツがあるようです。
この大きな石を施工区間の最下段に水平にしっかりと配置して安定化させます。ここが今後の作業や全体の出来栄えにも大きく影響するので気が抜けない重要な作業です。
最初の大きな石が配置できれば次に中くらいの石や、更にまた大きな石を要所に配置しつつ、段差を確保していきます。石がぐらつくようでは道は長持ちしませんし、何より登山者にとっても怪我や事故のリスクがあり危険です。私もやってみましたが限られたスペースに石を嵌め込み、ぐらつかないようにするのはとても難しく、まさに現場合わせの世界で直感と経験がものを言う世界だなと思いました。
現場監督の適切なご助言の下に作業を続けます。石を置く際は石同士が少なくとも3点、できれば4点が噛み合うようにすることが肝要です。指を挟みやすいので特に注意が必要です。そして、石の間の空間を小石や砂でしっかりと詰めていく作業により石を更に安定化させていきます。小石や砂は近くの沢で石箕(いしみ)という道具を用いて水で余計な土を洗い落として施工場所に運び作業を進めます。これなら私にもできそうだと思ったのも束の間、中腰の姿勢で作業を繰り返し何度か斜面を行き来する中ですぐに息切れ、情けない限りです。
とはいえ三人が協力してそれぞれにできる作業を進め、休憩を取りつつ、作業から4時間ほどで無事に作業を終えることができました。達成感はもちろんありましたが、4時間かけて人力で出来ることはこれだけなのかと思いつつも、常日頃登山道を直してくださっている方々への尊敬と感謝の念が自然と湧いて来ました。

施工中の様子(斜面上から)

施工完了(斜面下から)
夜の振り返りの時間では参加者から様々な感想や意見が出て私も大変勉強になりました。
道直しにおいて特に重要なポイントは上述した現場を最初にしっかりと観ること、点的に観るだけではなく生態系、風景、更には文化的な側面も含めて観るということが大切であるということです。加えて道直しの技術以上にそのマネジメントが重要であるということです。
私は「実践」と「実装」は使い分けています。
実践は一度限りのアクションで終わることも多く、実装は持続可能な仕組みと共に好循環をもたらすものです。マネジメントはこの実装に不可欠なものとも言えるでしょう。
また私自身今回の道直しに参加して多くの気づきを得ました。特に登山道を壊すのも人、直すのも人(自然の力を手助けする形ではありますが)ということで、様々な要因により山小屋の力だけでは道直しが難しくなって来ている現実の中で、今後、人と自然の新しい良い関係性を築いていく上で登山道はまさに生きた現場なのではないかということです。
道直しのためのボランティア、寄付、ファンクラブ、人材育成、事業化•収益化等様々な方策が考えられますが、まず、第一に言えるのは部外者がアレコレ言う前に日頃から現場をつぶさに観ている現場の方々がどうしたいか、どうありたいか、この内発的な視点が不可欠であるということです。その上で域外の人達との協働により現場でどのようなマネジメントや、持続可能な仕組みが良いのかを考えること、この順序が逆になり頓挫したプロジェクトを私も現場で何度も目にして来ました。私自身、北アルプスを愛する一人として外側の視点から行動し続けていきたいと思います。