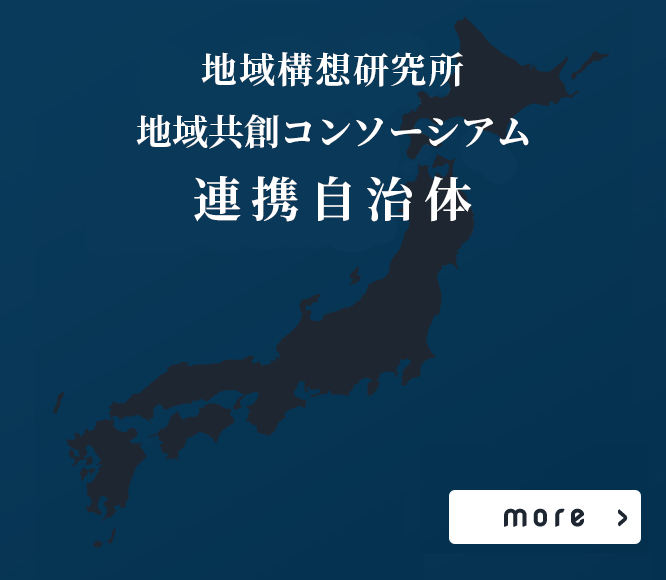石破茂首相が力を入れている防災庁設置構想に向けた作業が本格化した。去る1月30日には「防災庁設置準備アドバイザー会議」の第1回会合が開かれた。
その会合が開かれる少し前、旧知の赤沢亮正防災庁設置準備担当大臣とお会いする機会があり、防災庁の必要性や今後の防災体制のあり方に関する政府の認識を担当大臣から直接伺うことができた。ここでは、その時のやり取りを中心に、国の防災体制のあり方、自治体の防災行政の課題、防災に関する国と自治体との関係などについて、気がつくことを整理しておく。
防災庁設置に関する政府の認識
まず、国自身の防災体制についてである。現在の国の防災行政の司令塔は内閣府の防災担当部局だが、ここの職員のほとんどは関係各省からの出向者である。人事のローテーションで3年ほどすると親元の省に帰るので専門家が育ちにくい。防災庁を設置してプロパー職員を確保し、専門性の高い職員集団にしたいという。
また、これまで内閣府の防災担当大臣は、環境大臣や国家公安委員長などを兼務するのが通例で、「片手間感」が拭えない。防災庁を設置して専任の防災大臣を置くことによって司令塔機能を強化したいともいう。
次に、自治体の防災行政に関して赤沢大臣が問題視していたのは、地域によって防災行政に格差が見られるということだ。同じ国民でありながら住んでいる地域によって支援が手厚かったり、手薄だったりしている現状は解消すべきである。防災庁の中に地域担当を置き、それぞれの地域の防災体制を点検し、準備や体制に漏れがないようにしたいとのことだった。
防災庁設置構想の評価
以上の赤沢大臣ないし政府の認識については、概ね違和感はない。ただ、これまでの経験に照らすと、国と自治体との関係において、やり方を間違えると却ってまずくなりかねないとの懸念はある。
まず、内閣府の防災担当部局の職員のほとんどが他省からの出向者であるので専門家が育ちにくいとの大臣の指摘はそのとおりである。防災担当部局での経験が国の司令塔に蓄積しないのは実に勿体ない。全員ではないにしても、国の防災担当部門にはある程度の人数の専門家集団を配置しておくことが肝要である。
次に、防災担当大臣が他の国務大臣と兼務していることの弊害は私も実感したことがある。2010年9月に総務大臣として菅直人内閣の一員になったが、その時の防災担当大臣は環境大臣と兼務していた。
環境省ではその年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)のことに余念がなく、大臣もそれにかかりきりだった。いきおい防災行政に関与する時間は減り、そのことが翌年3月に発生した東日本大震災への対応に手抜かりがあったとは言えないが、もし防災専任大臣であったら、もう少し違った対応ができたのではないかとの悔いは残る。
自治体の防災行政には格差が見られる
防災行政に関して自治体によって格差があるとの赤沢大臣の指摘もそのとおりだと思う。その格差は平時には目に見えてはわからない。大災害に見舞われた時に、被災者の支援や復旧活動に迅速に当たれている自治体とそうでない自治体との格差が歴然とする。
もちろん災害によって被害の大小はあるし、被災地の地形や地勢が異なるので、単純に優劣をつけることはできない。ただ、それぞれの対応ぶりを見ていて、平素からよく準備をしていたことが窺われる自治体がある一方で、準備不足を疑わざるを得ない自治体があることも確かである。
後者の例では、九州のある県で大きな地震があった際、各地の避難所が大混乱を来したことがある。そこで混乱の原因を確かめてみようと、被災市町村の避難所開設・運営マニュアルをあたってみたところ、その時点では策定していなかったことがわかった。明らかに自治体の準備不足であり、混乱もむべなるかなとの印象を持った。
関東地方のある県では風水害により通信施設が甚大な被害を受けたことにより、県内の一部の地域との間で一切連絡が取れなくなった。そのような時のために、東日本大震災の教訓を踏まえ、衛星携帯電話を備蓄することが推奨されていた。その県では備蓄していなかったのかと思っていたところ、実は役所の倉庫にあることに誰も気づかなかったのだと、後日報じられた。これでは宝の持ち腐れである。
昨年大地震に見舞われた県でも広範に孤立した地域が発生したが、衛星携帯電話は使用されなかった。孤立する蓋然性が高い地域なので、該当の自治体の地域防災計画には衛星携帯電話の備蓄のことが記述されていたのに、財政上のことを考慮して配備には至らなかったという。これでは地域防災計画は絵に描いた餅でしかない。
地域の安全を自分ごととして本気で考える
こうした事例を耳にするにつけ、大事なことを疎かにしている自治体が少なくないという印象を拭えない。その大事なこととは、いざという時のことを自分ごととして本気で考えて準備をしておくということである。
いざという時のために準備しておくべきことは地域防災計画に書くことになっている。これを、トップを含む幹部が点検してみることが大切である。私が鳥取県知事をしていた時のことを引き合いに出すと、例えば避難所を設置するのは市町村だが、その避難所に食糧を供給するのは県の役割である。その食料は農水省の出先機関で精米を調達し、それを県が被災地に届けると地域防災計画には書いてあった。
それを見て、では精米をもらい受けた避難所はどうするかと考えた。被災地では電気もガスも水道も止まる。そんな時に精米を送り付けられた避難所は戸惑うだけだろう。そこで、地域防災計画を見直し、県は弁当仕出し業の組合と協定を結び、災害時には県の要請に応じて大量の弁当を供給してもらうことにした。この見直しは、その後に発生した鳥取県西部地震の際に大いに役立った。
先の衛星携帯電話の例では、事前の防災訓練の際に、孤立した集落が発生したことを想定し(当然そうした事態を想定しておくべきである)、衛星携帯電話を使って外部に連絡する訓練をしておけば、その段階で倉庫内に保管していることが関係者で共有される。あるいは、財政上の理由からまだ備蓄していないことが判明したら、トップは他に優先して衛星携帯電話の備蓄を指示するはずだ。
赤沢大臣の言う自治体間に見られる格差にはさまざまな要因や原因があるが、最も重要なことは、自治体のトップや幹部が地域の防災・安全について自分ごととして本気で考えているかどうかだと思う。自治体にそのことを気づいてもらうことが、国の防災行政の最重要課題の一つであるはずだ。
自治体の主体性を助長することが大切
先に、防災庁ができてもやり方を間違えると却ってまずいことになりかねないと述べた。間違ったやり方とは、例えば、国が防災庁設置を契機に本来自治体がやるべき防災行政の領域まで取り仕切ろうとすることである。
昨今、厄介なことは国に責任を持ってもらうのがよいと考える自治体が少なくない。そんな中で国が自治体の役割にまで手を出すと、自治体はこれ幸いに自分の役割から手を引きかねない。そもそも防災行政はその準備の段階でも、被災者支援や復旧の段階でも、地域でしかわからないことが多くある。それにも拘らず自治体が手を引けば、被災者にとってピントのずれた支援になりかねない。
防災行政における国と自治体との関係では、国はあくまでも自治体の主体性を喚起することに徹し、自治体が地域の安全を自分ごととしてとらえ、いざという時には持てる力をフルに発揮できるよう促すことを旨とすべきだと思う。
以上のことが防災庁設置に向けての議論や今後のわが国の防災行政の中でいささかなりとも参考になることを願っている。