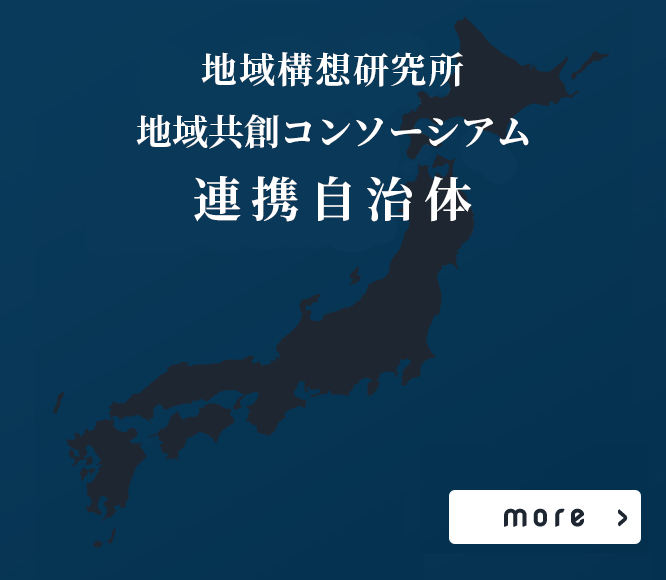1.はじめに
せんだいメディアテークは、宮城県仙台市にあるユニークな公共施設である。2001年の開館以来、先進的な図書館、美術館、映像センターとしての機能を統合し、市民の創造性と文化活動を育む拠点として注目を集めてきた。この施設は、従来の行政サービスとしての図書館や公民館の枠を超え、市民一人ひとりの能動的な参加を促す新しい公共空間のモデルを提示している。
図書館はバリアフリー・サービス、児童サービスに力を入れている。両者に力を入れていることは、図書館がインクルーシブな社会を目指していることを私たちに示唆している。
哲学者の鷲田清一が2013(平成25)年4月より館長を務めた。2025(令和7)年4月からは、日本文学研究者のロバート キャンベル氏(東京大学名誉教授、早稲田大学特命教授、国文学研究資料館前館長)が新たに館長に就任した。
2.建築デザイン —空間と活動を融合させる—
せんだいメディアテークの最大の特徴は、世界的建築家である伊東豊雄氏が設計した独創的な建築デザインである。ガラス張りの外壁、そして施設全体を貫く13本の「チューブ」と称される鉄骨の柱が、開放的で自由な空間を生み出している。これらのチューブは、単なる構造体ではなく、エレベーター、階段、配管、配線といった機能を内包しており、空間のアクセシビリティを確保している。この「チューブ・イン・チューブ」構造は、従来の建物の堅牢さとは対照的に、軽やかで透明感のある雰囲気を醸し出し、外部の街並みと内部の活動がシームレスにつながるように設計されている。
このような透明性と流動性を重視した設計思想は、施設運営の理念にも通じている。固定された壁や境界線を持たない空間は、用途を限定せず、様々な活動やイベントに柔軟に対応できるため、従来の公共施設にはない多様な交流と活動の可能性を生み出している。

せんだいメディアテークの外観 ガラス張りの美しい建築

現代的で機能的な館内デザイン
3.多様な機能と活動 —市民の創造性を育むプラットフォーム—
せんだいメディアテークは、単一の機能に特化するのではなく、複合的な機能を内包している。
従来の図書貸出に加え、市民が企画・運営する読書会やワークショップが盛んに行われている。
一躍せんだいメディアテークを全国的に有名にしたのは、哲学者の鷲田清一氏が企画・運営に携わった「哲学カフェ」である。市民が参加し、鷲田氏の運営によって暮らしや社会に関わるテーマについて自由に語り合う場である。
現代美術の企画展や、市民参加型の展示が定期的に開催されている。
私が訪問した10月の晩、1階のアートスペースでは福島県葛尾村で実施されたKatsurao Collectiveのインスタレーションが開催されて、大きなスクリーンには葛尾村の映像と共に村民の語りの声が流されていた。村民は、豊かな自然が残された故郷への思いを滔々と語る。その声の背景となる村の状況に思いを致すとき、胸が強く締めつけられる。
葛尾村は2011年に福島第一原子力発電所による原子力災害を受け、村民の全損避難が余儀なくされた。現在では、一部を除き規制が解除され、帰村者と震災後の転入者が村内で暮らしている。Katsurao Collectiveは移住・定住促進の一環として、アーティスト・クリエイターを短期移住者として地域に迎え入れるプラットフォームづくりを行なっている(『Katsurao Collective Report2024』による)。
このほかにも館内では、映画の上映や、市民向けの映像制作ワークショップが提供されている。
これらの機能はそれぞれが独立しているのではなく、有機的に連携している。例えば、美術展のテーマに関連した図書を特集したり、映像作品の制作プロセスを学ぶワークショップを開催したりするなど、異なる分野の活動が相互に影響し合うことで、市民の知的好奇心と創造性を刺激している。
また、特筆すべきは、市民の主体的な活動を強く支援している点だ。「フリースペース」と呼ばれる開かれた空間は、市民グループが自由にミーティングやイベントを開催できる場として提供されており、ここから多くのユニークなプロジェクトが生まれている。このような運営方針は、施設を単に利用する場所としてではなく、市民自身が文化を創造し、発信する拠点として機能させている。
私が訪ねた10月の晩には、仙台市内の大学の建築学を学ぶ学生の自主的な交流会が持たれていた。

明るい外光が入る交流スペース
4.先進的な公共施設の意義と位置付け
せんだいメディアテークの取り組みは、これからの自治体が目指すべき公共施設のあり方について、重要な示唆を与えている。
①「所有から利用へ」の転換
従来の公共施設は、行政が情報やサービスを所有し、市民に提供するという一方的なモデルが主流だった。しかし、せんだいメディアテークは、市民が持つ知識、スキル、創造性を引き出し、市民自身が主役となって文化を創り出すことを促している。これは、行政が一方的にサービスを提供するような「箱モノ」ではなく、市民の「活動のプラットフォーム」としての役割を担っていることを意味する。このような転換は、住民のニーズが多様化し、情報が氾濫する現代社会において、持続可能で活気のある地域社会を築くために不可欠な視点といえる。
②分野横断的なコラボレーションの促進
現代社会が直面する課題は、図書館、美術館、映像センターといった単一の専門分野だけでは解決できない複雑なものだ。せんだいメディアテークのように、異なる分野の活動が交差する空間は、分野横断的なコラボレーションを自然に生み出す。
例えば、地域の課題をテーマにしたドキュメンタリー映画を制作し、その上映会と関連する書籍の展示を同時に開催することで、多角的な視点から課題を掘り下げ、解決策を探る議論が生まれる。このような「知の交差点」としての機能は、社会全体にイノベーションをもたらす可能性を秘めている。
5. 「居場所」としての役割
コロナ禍は人々の交流を分断し、孤立や孤独を招いた。その影響は私たちが見えないところで、いまも影響していると思われる。
せんだいメディアテークは、単なる文化施設を超えて、市民の「居場所」として機能している。ガラス張りの開放的な空間は、誰もが気軽に立ち寄ることができ、年齢や背景の異なる人々が自然に出会い、交流する場を提供している。特に東日本大震災後、この施設は市民の精神的な支えとなり、コミュニティの再構築に貢献した。公共施設が、災害時を含むあらゆる状況において、安心できる居場所としての役割を担うことは、社会のレジリエンス(回復力)を高める上で極めて重要である。
私が訪ねた晩は、図書館が20時で閉館した後も、最上階のフリースペースでは、椅子のないカウンターでは、多くの高校生たちが、バッグや部活動の用具を横に置いて立った姿勢のまま勉強に集中していた。
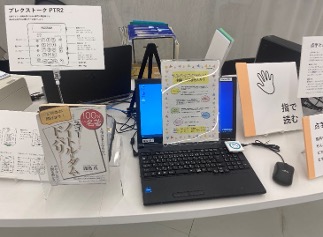
図書館では充実したバリアフリー・サービスを展開
6.終わりに
せんだいメディアテークは、従来の公共施設の枠組みを大胆に解体し、市民の創造性、活動、そして交流を育む新しい公共空間のモデルを提示した。その取り組みは、建築、運営、理念のすべてが一体となり、市民を「利用者」から「主体」へと位置付け直すため、いまも画期的な挑戦を続けている。
せんだいメディアテークは、人口減少や高齢化が進む日本において、各自治体が直面する「公共空間の再定義」という課題に対する一つの有効な回答を示している。これからの公共施設は、単なるサービス提供の場ではなく、市民の潜在的な力を引き出し、多様な交流を促進するプラットフォームとして機能する必要がある。このような施設の創出と運営は、地域社会の活性化と持続可能性を確保するための重要な戦略である。
自治体は、同館の先進的な事例から多くを学び、それぞれの地域に合った形で新しい公共空間を創造していくことが求められる。せんだいメディアテークは、その未来に向けた羅針盤となる存在といえるだろう。