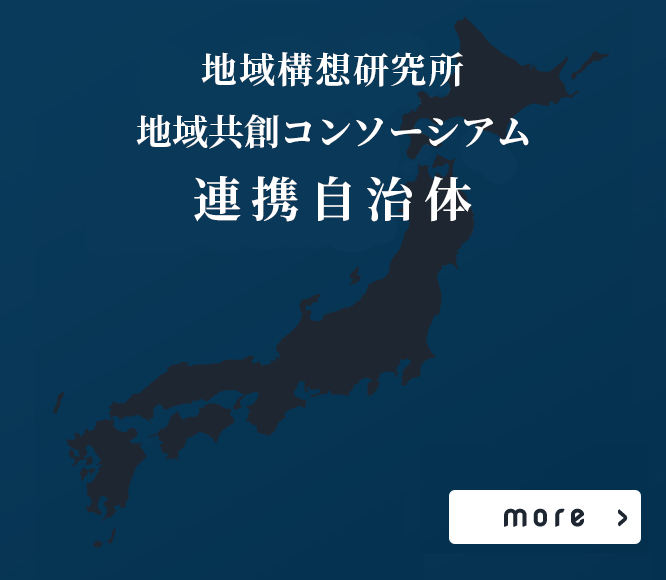皆様、こんにちは。大正大学地域構想研究所 淡路支局長の山中昌幸です。私は、当研究所の淡路支局を拠点に、地域共創をテーマとした活動に取り組んでいます。
日本各地では、人口減少、高齢化、若者流出、地域経済の縮小といった課題が深刻化しています。これらに対し、従来の行政主導の一過性の施策だけでは解決が難しいのが現状です。今こそ、地域に根差したボトムアップのアプローチによる、多様な人々が力を合わせる「共創」が欠かせません。従来のトップダウン型ではなく、住民や若者が主体となる取り組みこそが、持続可能な未来を築く鍵なのです。
この共創を実現するため、淡路支局は大学発ローカルベンチャーである株式会社次世代共創企画と共同で、淡路ラボという地域共創プラットフォームを立ち上げました。ミッションは「国はじまりの島から未来を共創する」、ビジョンは「響きあう地球」です。地域や立場、国籍を超えて、多様な人々の強みが響き合い、新しい価値を創造していくという思いが込められています。
淡路支局では、このプラットフォームを運営し、多岐にわたる活動を展開してきました。特に、淡路市と連携した「地域実習」は、学生が主体的に地域課題に取り組む重要な活動です。これまでの5年間で64名の学生が参加し、具体的な成果を生み出しています。
2024年度に実施した地域実習では、淡路島での暮らしや仕事の魅力を探究する「はたらく」をテーマに、学生が主体的に活動しました。地域住民や事業者へのインタビューを通して、淡路市の魅力を都会に伝えるフライヤーを作成するなど、具体的な成果を生み出しました。

2024年度地域実習(事業者訪問)

2024年地域実習(淡路の地場産業である香りづくり体験)
また、2025年度に実施を予定している地域実習では、「関係人口を育む」をテーマに、過去の参加者を含むコミュニティ構築を目指すプロジェクトを実践しています。学生たちは、若手社員や移住者へのインタビューを行い、その知見をもとに東京の大学キャンパスで淡路島の食材を使った料理を提供する「淡路カフェ(仮称)」を企画・運営するなど、具体的な取り組みを進めています。
さらに、淡路市連携大学まちづくり活動補助金を活用した活動も行っています。2024年度に実施したプロジェクト「東京巣鴨と淡路市との共生プロジェクト」では、大学のアンテナショップでの淡路フェア開催や移住希望者との交流会を通じて、都市と地方の交流を実践的に学びました。そして、2025年度も同プロジェクトを実施予定で、7月には過去の参加学生と今年の参加学生を対象とした交流会を大学で開催しました。今後は、地域実習終了後にコミュニティカフェ「淡路カフェ(仮称)」を大正大学のアンテナショップ等で実施し、これまでの参加学生や移住や仕事に興味を持つ都市住民との関係性をさらに深めることを目指しています。

淡路市PRを東京で行う学生(2024年度大学まちづくり助成金活動)
他にも、若者対象の長期実践型インターンシップや、「裏万博構想」として島全体をパビリオンに見立てる取り組み、世界青年の船事業も実施しました。JALやロート製薬など大手企業約20社が参加するカンファレンスでは現地事務局として対応し、淡路島での企業連携を促進しました。
その他の活動としてAuthentic Japanと島の人事部を展開しています。Authentic Japanは地域の暮らしに精通したガイドが特別な旅を提供し、島の人事部は人材不足の課題に対し多様な働き方で地域と関わる仕組みです。
これらの淡路支局の活動から、私たちは持続可能な地域共創のための7つの要素を見出しました。
1. つなぎ役という「人」の存在と信用力: 異なるステークホルダーの強みを掛け合わせる「つなぎ役」となる人材は不可欠です。大正大学と淡路市の包括連携協定が活動の信頼基盤です。
2. ビジョンの共有: 「響きあう地球」というビジョンを掲げ、多様なステークホルダーと共有することで、活動が一体となって進みます。
3. 協働者選定と強みの活用: 協働の意思があり、強みを活かした役割分担ができる「人」とともに行うことで、単独では成し得ない成果を生み出します。
4. 共創プロセス「まぜる→つながる→うまれる」: 多様性が新しい価値を生む場を作り、この流れで進めます。
5. 「いる→なる→する」の考え方: まず地域に「いる」ことで人や地域を知り、その中で役割を担う「なる」段階へ進み、そして「する」という行動に移します。
6. 経済的持続可能な仕組み: 委託、補助、事業など多様な資金調達に加え、補助金を「投資」として自主事業を強化します。
7. 自力でやろうとしない運営体制: 人件費確保に縛られないよう、学生や地域おこし協力隊等を積極的に活用し、フラットなネットワーク型組織を構築します。
これらの知見は、淡路島だけにとどまりません。私たちはこのモデルを全国と共有し、共に発展していきたいと考えています。
ご興味のある方はこちらのアドレス(m_yamanaka@mail.tais.ac.jp)までお気軽にご連絡ください。