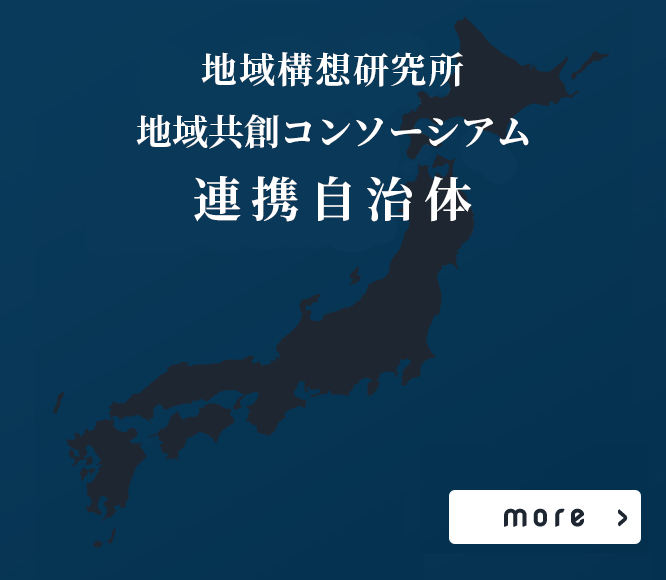これまでの私のレポートでは、「人口減少を所与のものとして受け入れた上で、住民のウェルビーイングを維持し、高めて行くことを目指す」という「スマートシュリンク(賢く縮む)」の考えについてたびたび取り上げてきた。また、このスマートシュリンクの考えが、なぜか今年(2025年)に入ってから急にマスコミでも取り上げられるようになり、私が結構な頻度でマスコミの取材を受けるようになったことも紹介した。 急に各方面で関心を持たれるようになった理由は良く分からないのだが、①人口減少をストップさせることは難しいという認識が広まってきたこと、②石破内閣で進められつつあった「地方創生2.0」においても、スマートシュリンクと同様の考えが示されたこと、などがあったとも考えられるのだが、さらに、最近、現にスマートシュリンクを実践している自治体が現れてきたことも影響しているのかもしれない。
その実践自治体の例として、岡山県美咲町と山梨県早川町を紹介しよう。
美咲町については、当研究所が主催している地域戦略人材塾に同町の青野高陽町長をお招きしたことがある。青野町長が就任した2018年当初は、町は県内でもワーストの人口減少率で、総合計画も期限を過ぎているという状態だった。その町政を再建していく過程で生まれてきたのが「賢く収縮するまちづくり(スマートシュリンク)」という基本方針である。
そのきっかけになったのは、公共施設の見直しだった。町長就任時は、町民一人当たりの公共施設の床面積が全国平均の2倍以上もあった。これを人口規模に見合って集約・縮小していくことがスマートシュリンクの出発点となった。そこで、2年かけて全施設のカルテをつくり、1人あたりの利用コスト、耐用年数などから優先順位をつけ、学校関連、プール、温泉施設、公民館など約60の施設について解体や売却を進めている。もちろん縮小だけでは住民のウェルビーイングは低下するばかりなので、新たな施設も作る。しかし、新しく作る際には複数の施設を一体的に整備し、建設資材も簡素なものにするといった工夫をしている。例えば、同町の多世代交流拠点には、公民館、図書館、保健センター、社会福祉協議会が一体的に整備されている。
こうした他にも工夫を講じている。そのひとつが、小規模多機能自治体の推進である。これは、住民自身が地域の課題を洗い出して解決策を実行する仕組みである。高齢化率が高まる中、個人や自治会単独では課題への対処が難しくなったことから、81の自治会を13のグループに分けて、より大きな単位で補完し支え合うのが狙いである。中学生以上の全員にアンケート調査して地域の課題を調べ、優先順位を付けた上で、道路・河川の美化、高齢者の見守り等の活動を行っている。
さらに、過疎化が深刻な2地域では、小中学校の義務教育を一体化した義務教育学校を設けた。小中学校を一つにすることで、児童・生徒数を確保し、学校を地域に残せるようにしたのである。過疎地における教育施設のモデルとして、海外からも含めて多くの視察者が訪れるという。
もう一つの、山梨県早川町の例は、私も、NHKの取材を受けて初めて知ることになったものである。本年の10月のある日、NHKの「おはよう日本」という番組の担当者から、スマートシュリンクの考え方について取材したいという話が飛び込んできた。なお、ついでに言っておくと、これらマスコミ関係者は、「この問題について誰に取材しようか」という時には、まずネットで検索するようだ。試しに「スマートシュリンク」「賢く縮む」というワードで検索してみると、上位にかなりの数で大正大学地域構想研究所のアウトプットが出てきて、その多くに私の名前が出てくる。今やネットの時代だから、検索にひっかからないと、マスコミも取り上げてくれないのである。
さてこの取材を受けた番組は、10月3日の朝、放送された。以下、番組に沿って紹介しよう。
番組ではまず、スマートシュリンクというのは「人口減少を食い止める」のではなく「人口減少は避けられない」という前提のもとに、自治体の事業を取捨選択し、住民に必要なサービスの維持・向上を図っていくという考えだということが紹介される。
その例として紹介されたのが山梨県の早川町である。早川町は昭和30年代には、ダムや発電所の建設などもあって、およそ1万人が暮らしていたのだが、現在では人口は約800人まで減っている。全国で最も人口が少ない町だという。
早川町は、一時は町を再び活性化しようと、数億円をかけて観光施設を建設したりしたのだが、人口減少に歯止めをかけることはできなかった。そこで、2024年に就任した深沢肇町長は、「人口が減っても安心して生活できる環境を整える」ことを最優先に、お金の使い道を抜本的に見直すことにした。プロジェクトチームを立ち上げ、約50の事業の必要性・妥当性を検証した。例えば、老朽化していた温泉施設の休業を決め、年間約900万円の経費を削減した。こうして見直した予算で、住民福祉に欠かせない水道や病院を維持することとした。
番組では、本年9月にオープンした町で初めてのコンビニも紹介された。このコンビニはそれまであった直売所を改築して作った町営のコンビニで、食品や日用品を中心に1000点以上の商品が並んでいる。町長の深澤肇氏は、「住民の福祉住民のためになるには、何でもやるではなく、何が生活に密着した住民のためになることかを考えた」と話す。
ここで専門家(私のことです)が登場し、「自治体に問われているのは、予算の使い方が住民福祉にどの態度役立っているのかを検証した上で、賢く縮む策を打ち出すことが出来るかどうかということです」と述べている。
この美咲町や早川町の例は、スマートシュリンクを掲げた地域政策の推進は、身の丈に合った背伸びをしないで、地域の人々のウェルビーイングの維持・向上を目指すべきであること、それを進めるためには、公共施設の整備、教育体制、住民自治の仕組みなどについて、各分野での工夫の積み重ねが求められること、そして、人口減によって厳しい状況に置かれている地域においても、住民のウェルビーイング向上は可能であることを示しているように思われる。
岡山県美咲町と山梨県早川町の例
2025.11.17