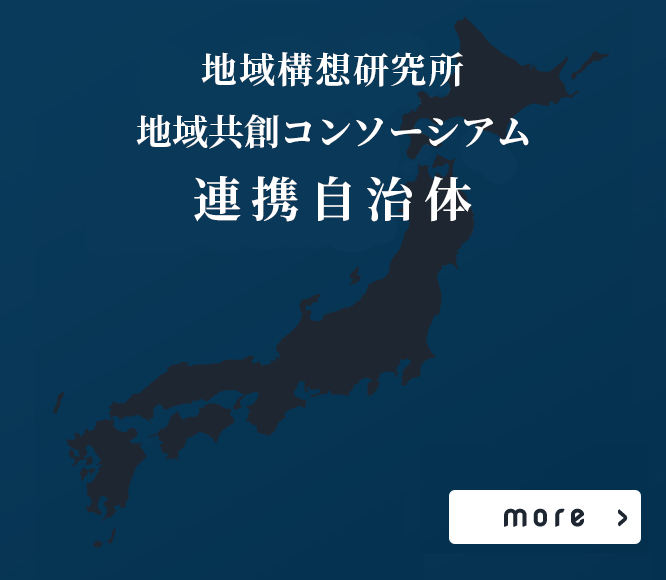私がベースにしている学問体系は「経済学」である。その私が、経済学の中で最も気に入っている点は、それが「人々の自由な活動」をベースにしていることである。経済学の基礎理論で、大学で必ず学ぶ分野に「ミクロ経済学(または価格理論)」がある。このミクロ経済学の基本中の基本は「人々が自由に自分の利益の最大化を実現しようと行動することが、結果的に一国全体の経済的利益を最大化する」という命題であると。いわゆる「市場原理」である。世の中では、あまりこの市場原理を振りかざした議論をすると、「弱肉強食を認める市場原理主義者」というレッテルを貼られたりするのだが、私はこの市場原理を信奉している。「自由」ということは素晴らしいと考えるからである。人々は誰にも邪魔されずに、自由に経済的活動を営んで良い。逆に政府は、個人の自由を損なうような余計な介入はすべきでない。その代わり、自分の運命は基本的には自分の責任で切り開くものなのだから、その結果がどうなろうと愚痴を言ってはいけない。これが私の基本的な経済観である。
ここから突然地域問題の実践論になるのだが、スマートシュリンク(人口減少を所与とした上で地域住民のウェルビーイングを高めて行くという政策方向)の実践として私が強調したいことは、自由な人の移動を通じたスマートシュリンクである。理想的過ぎて現実味に欠けると思われる人も多いだろうが、それは次のような考えである。
スマートシュリンクが地域にもたらす困難の原因は、「集積の利益」が失われることである。人口が減ってもその集積の利益を保つ一つの道は、人口密度が低下して集積利益が失われた地域から人々が移動して集まることだ。いわゆるコンパクト化である。この時、人々が自由な意思でそうした移動を行ってくれるのが理想的である。「そんなことが出来るなら苦労はない」と思う人が多いだろうが、少しでもそれに近づくようにしてはどうかと私は考えている。
そのためには、まず将来を適切に見据えた人口見通しと住民サービスの将来展望を明らかにすることが求められる。現在、各自治体で示されている人口の展望は、「人口減少を止めたい」という政策的目標の要素が含まれているので、どうしても見通しが甘めになる。まずは地域の人々に「長期的に見ると、自分が居住する地域の人口はこうなるのか」という正直な姿を知ってもらう必要がある。
そして(ここからが難しいが)、この地域では長期的に見るといくつかの住民サービス(医療、教育、交通、商業等)が受けられなくなるか、受けられたとしても高コストになるという見通しを示す。こうした見通しを早めに示しておけば、「それでも住み続けたい」という人々は住み続けるだろうし、「そんなに不便になるなら今のうちに利便性の高い地域に移住しよう」という人は自主的に移住するはずだ。自治体が地域住民にこうしたマイナスの情報を伝えるのは現実には難しいだろうが、これが実現すれば、予算を投じて政策的にコンパクト化を進めないでも、人々の自由意思に基づくスマートシュリンクが実現するはずだ。
自由に人が移動することは、スマートシュリンクだけではなく、多くの地域問題の解決にも資する。人口が減りつつある地方部では、都市部からの移住者の受け入れに力を入れている。実際に、都市部に住む人々の中で地方移住への関心を持つ人は多い。国土交通省が東京圏在住者を対象に行った調査によると、全体では35.1%、20代では44.8%が地方移住に関心があると答えている(国土交通省「2024年版首都圏白書」)。こうした移住希望が実現すれば、地方から大都市圏への人口の流出という大きな課題が相当程度緩和されることになる。
しかし、現実に居住地を変えるためには多くのハードルがある。すると、こうした自由な居住地移動を妨げているハードルを出来るだけ低くしていくことが地域問題の鍵を握ることになる。例えば次のようなことがある。
まず、居住地を変える場合には、「持ち家主義」が高いハードルになる。戦後の日本では持ち家を取得することが推奨され、政策的にも低利の住宅ローン、住宅減税などの措置が取られてきた。人々の価値観としても「いつかは自分の城としての持ち家を持つ」ことが当然のこととされていた。このため、貸家は単身世帯や結婚後間もない世帯用のものが中心となっている。
この持ち家主義は居住地の移動を妨げる。引退後はそれまでの都市部を離れて、自然に囲まれた地方で過ごしたいと思っても、移住のためには都市部に持っている住宅を売却する必要がある。しかし、自分の城として住み続けた持ち家は、他人にとっては住みにくいことが多いので、売却する時に価値が大幅に下がり、思うように売却できない。これが貸家であれば、住宅の住み替えのハードルはずっと小さくなるはずだ。
働くという点では、終身雇用的な慣行が人の移動を妨げている。大都市での通勤地獄と狭隘な住宅事情を逃れ、地方部でゆったりした暮らしをしたいと考えても、そのためには働く場が必要だ。ところが日本では、一つの企業で定年まで働き続けることが標準モデルとなっている。退職金制度など、長く働くことが有利な制度もあるので、無理に退職すると不利益を被ることになってしまう。住みたいと思っている地域で仕事を見つけるのが難しく、今の仕事をやめるとペナルティがあるのでは、地域を移動することは難しくなる。もし、労働力の流動化が進み、企業の垣根を超えて自分の能力に見合った職場が見出せるようになれば地域の移動はもっと円滑に進むようになるだろう。
農地の取得が難しいという問題もある。日本では、農地を取得するには農業委員会の許可が必要であり、その許可を得るには、農地の規模、農業経営能力などについての条件を満たす必要がある。企業の農地保有についても制約がある。このため、都市部に住む人が農業をやりたいと思っても、農地の取得がネックになる可能性がある。企業が農業を営んでいれば、その企業に勤務して農業に従事するということも可能になるが、それも難しい。個人、企業の農地取得がもう少し自由化されれば、非農業地域から農業地域への人の移動が活発化するのではないかと思われる。
どんな問題についても、解決しようとすると、政府にいろいろ政策要望を出すことが基本になることが多いのだが、「新しい政策を打つよりも、もっと我々の自由な行動の範囲を広げて欲しい」という要求もあっていいように思う。
経済学と「自由」
2025.10.15