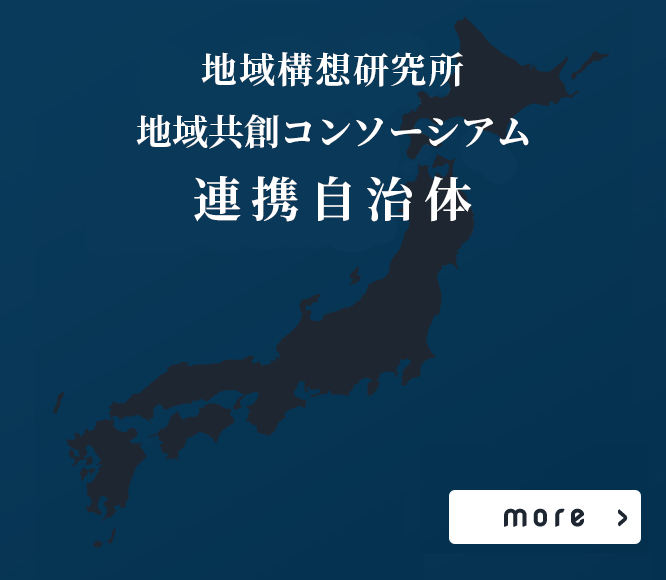このところ「スマートシュリンク(賢く縮む)」という考え方について、マスコミから取材を受けることが多くなった。私は、かなり前から「スマートシュリンク」という考え方を主張しているのだが、某マスコミの取材で「小峰さんはいつごろからスマートシュリンクを主張しているのですか」という質問を受けた。そこで、過去に書いたものを調べてみると、2017年3月に出版した「日本経済論講義」という本で、「これから求められているのはスマートシュリンク」という項目を立てて、議論を展開している。10年ほど前からこの主張をしていたことが分かった。
ただ、当初は私自身、多くの人の前で「これからはスマートシュリンクで行きましょう」と堂々と発言するのは控えてきた。それが、最近になって多くの人に抵抗なく受け入れられるようになり、私自身も遠慮なく主張を展開できるようになった。これがどうしてなのかを考えてみよう。
私は、長い間スマートシュリンクの主張を展開しているうちに、この主張の大きな柱は次の三つだと思うようになった。それは「人口減少は避けがたいこと」「少子化対策に政策資源を投入するのは慎重にすべきであること」「人口が減っても人々のウェル・ビーイングを高めていくことは十分可能であること」という三つである。振り返ってみると、当初の段階で私が、多くの人の前でスマートシュリンク論を発言しにくかったのは、この三つの柱が制約になっていたからだと思われる。
まず「人口減少は避けがたい」という第1の柱だが、かつてはこういう主張をすると「では少子化対策を諦めるのですか」という批判を招きそうな雰囲気であった。2014年から推進された政府の地方創生(いわゆる「地方創生1.0」)は、直前に登場した消滅自治体論を受けて、地方創生と人口減少という二つの課題を同時解決しようとするものだったからだ。「人口減少をストップさせることはできない」と主張することは、地方創生1.0そのものに冷や水を浴びせるようなものだったのである
第2の柱「少子化対策は慎重に」というのも同じである。地方創生1.0の下で、各地域は競って少子化対策を進め「人口減少をストップさせた自治体が成功自治体」とみなされるような雰囲気が醸成された。地方創生1.0では、国の人口ビジョンとして、総人口1億人程度を実現するために「2020 年に出生率1.6 程度、2030 年1.8 程度、2040 年に人口置換水準(2.07)」という想定を示している。これにならって策定された各地域の人口ビジョンでは、同様の出生率が想定されたのである。なお、ここで登場する1.8という出生率は、「結婚したい人は全て結婚し、産みたい子供は全て産むとした場合、つまり、すべての人の希望がかなえられた場合の希望出生率のことである。こうして全ての自治体が人口一億人を目指して少子化政策に力を入れているまっただ中で、「無駄な少子化対策は止めましょう」と主張するのは難しかったのである。
第3の柱については、人口が減っても人々のウェル・ビーイングを高めることが本当に可能なのかが大きな焦点となる。この点については、そもそも地方創生1.0は「人口減少が続くと地域は消滅の危機に瀕するほど大変なことになる」という認識で出発しているわけだから、「人口が減っても人々は幸せになれます」という主張は全く相手にされなかったのである。
こうして見ると、当初の段階でスマートシュリンク論の主張が各方面から受け入れがたいものだったことにはそれなりの背景があったことが分かる。では、最近になって多くの人に受け入れられるようになった(ように感じられる)のはなぜだろうか。これにもそれなりの背景がありそうだ。
まず第1の柱については、もはや誰もが「人口減少をストップさせることはできない」と感じるようになった。人口は減り続けており、しかもそのスピードは加速している。前述の希望出生率を現時点で計算すると、1.6程度になっている。全ての人の希望が実現しても、1.6なのだから、どんなに頑張っても、置き換え水準2.07に届くはずがない。
第2の柱については、多くの人が「地方が主体となって少子化対策を進めるのはどこかおかしい」と感じるようになった。少子化対策の効果が出た自治体では確かに人口が増えている。しかしそれは、手厚い優遇措置を講じて、近隣自治体から子育て世帯を呼び寄せたからである。その場合、子育て世帯が出て行った近隣自治体では、出生率が下がり、人口はさらに減る。要するに子育て世帯の取り合いというゼロサムゲームなのである。
第3の柱については、データが蓄積されてきたことが大きい。日本全体の人口は2010年頃から減少し続けているのだが、この間のデータを見ると、日本全体の経済は人口減少下でも拡大しており、一人当たり所得も増え続けている。都道府県レベルでも、県民総生産や一人当たり県民所得は増え続けている。少なくとも都道府県レベルでは「人口が減っても、人々のウェル・ビーイングは高まる」というスマートシュリンクが実現しているのである。
ただし、市町村レベルでも同じことが起きているとは言えない。そこから先は各地域の取り組み次第となるだろう。この点については、近年スマートシュリンクを地域行政のキーワードとして掲げる自治体が現れてきたことは心強い。例えば、岡山県美咲町では、青野高陽町長の下で「賢く収縮するまちづくり」を掲げて行政を進めており、住民間で自治組織を作って行政に協力する体制を敷いているほか、小・中学校の一体化、公的施設の集約などの施策を展開している。また、高知県では、「人口減少社会に適応し『賢く縮む』4Sプロジェクト(『集合』『伸長』『縮小』『創造』)」を推進している。
スマートシュリンクは多くの人に受け入れられ、既に実践段階に入っているのである。
スマートシュリンク論の変遷
2025.09.16