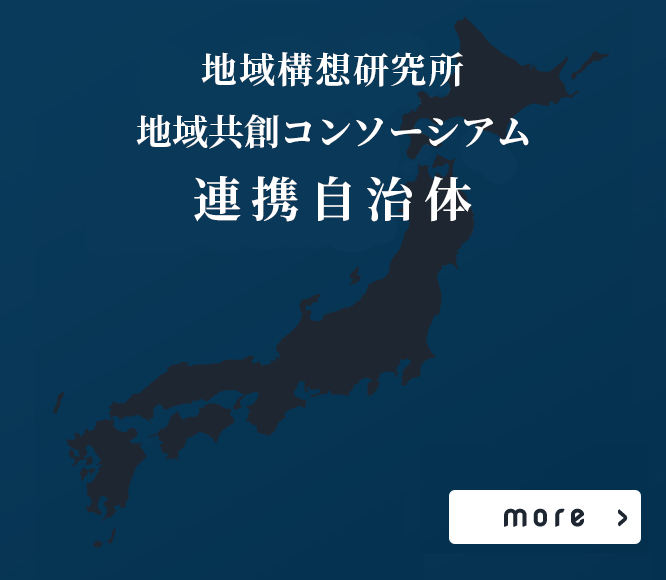前回の「幸福度について考える」では、石破総理の所信表明演説で、総合的な「幸福度・満足度」の指標を策定するという方針が示されたことを述べ、2009年に発足した民主党鳩山内閣の時にも同じような議論があり、これがきっかけとなって、幸福度についての研究が進み、それが今なお続いていることを紹介した。
その各方面における調査研究で分かってきたことは二つある。一つは、どんなことが人々の幸福度・満足度と関係しているかということである。内閣府経済社会総合研究所では、2012年3月には大規模なアンケート調査を行った。この調査から、おおよそ次のようなことが分かってきた。
①所得水準が高くなるほど、幸福度は高く、更に、かなり明瞭に「生活のやりくりが容易である」人ほど幸福度が高い、②仕事をしている人は総じて幸福感が高く、仕事を探している人(失業者)は幸福感が非常に低い、③結婚している人の方が幸福感が高い、④健康な人ほど幸福感が高い、⑤学歴が高いほど幸福感が高い、⑥困難な時に助けてくれる人の数が多いほど幸福感が高い、といった具合である。いずれも常識的な結果だと思うが、これを見て私は次のように感じた。
第1に、私のような経済学者が日頃から重視している、オーソドックスな経済政策の目標を達成することは、人々の幸せのためにも大変重要なのだと改めて感じた。経済政策の大きな目標は、サステナブルな形でできるだけ高い成長率を実現し(できるだけ高い所得水準を実現し)、失業率を引き下げ(働きたい人に働く場があるようにする)、物価を安定化させることだ。適切な経済政策によってこれらが達成されれば、人々の生活は安定し、失業率も下がるから、人々の幸福感は高まるはずだ。
第2に、幸せに関係するからといって、政府が直接介入すべきかどうかは疑問だと思われる分野も多い。例えば「結婚している人」「学歴の高い人」の方が幸福度が高いからといって、政策的に結婚や高学歴を奨励すべきかどうかは疑問である。世の中には「結婚しない」「学歴にはこだわらない」という生き方を選択している人も多いからだ。
政策的に対応すべきなのは「結婚したくても経済的な理由で結婚を諦めている人」や「より高い教育を受けたくても受けられない人」にそれができるような環境を整備していくことだ。それはまた、できるだけ所得を引き上げ、生活を楽にするということでもある。
第3に、そもそも政策的に対応することが難しい分野もある。例えば、どうすれば「身の回りに助けてくれる人がいる」という状態を作り出すことができるのだろうか。個人のプライバシーを侵さない形で、それをどう実現するのか。これはなかなか難しい問題だ。
「人々を幸せにしたい」という動機は正しいとしても、だからといって「直接的に人々の幸せを高めようとする」ことが良い政策になるとは限らない。人々はそれぞれ自らの価値観に基づいて自らの幸せを追求しているのだから、政府は低所得、失業、デフレ状態などを防ぐことにより、間接的に人々が幸せを追求しやすいような環境を整えることを目指せばよい。それが人々を幸せにする最も効率的な政策であるというのが私の考えだ。
2011年以降の各方面における調査研究で分かってきたもう一つのことは、幸福度または満足度が、時間の経過とともにどのように変化しているのかである。
内閣府では2019年から「満足度・生活の質に関する調査」を継続的に行ってきている。この調査では、主観的ウェルビーイングの指標として「現在の生活にどの程度満足しているか」を10段階で自己評価した結果を集計している。本論の冒頭で、石破総理が「総合的な『幸福度・満足度』の指標を策定する」という方針を示したことを紹介したが、その「総合的な幸福度・満足度に関する指標」は既に存在しており、各年の推移を見ることもできるのである。
その満足度の推移を見ると、調査が始まった2019年の時点では、全体の満足度は5.78だったのだが、2021年には5.74まで低下している。これは新型コロナの影響であろう。その後、最新時点(2024年)では5.89まで上昇している。これは調査開始以来の最高値である。2024年に満足度が高まったのは、日本経済が、デフレから脱却し、賃金も近年にない上昇となったからだと思われる。この調査では、雇用形態別の満足度が分かるのだが、2023年から2024年にかけては、正規雇用の就業者の満足度が5.76から5.85に、非正規雇用の就業者の満足度が5.52から5.67へと上昇していることからもそれが分かる。
しかし私から見ると、こうした意識調査による人々の満足度(または幸福度)を経済政策の目標として位置づけることについては疑問がある。人々の意識は移ろいやすい。私がちょうどゴールデンウィーク中の読書で手にしているエリック・アングナー「経済学者のすごい思考法」(早川書房、2024年11月)では、幸福の経済学についての解説があり、「人々は環境に慣れてしまうので、同じような経済状態でも幸福度は低下する」「人々の願望水準が高いと、経済状態が好転しても幸福度は高まらない」「人々の幸福度は経済状態の絶対水準ではなく、他の人と比較した相対水準で決まる」といったことが指摘されている。つまり、経済政策のよろしきを得て経済パフォーマンスが改善しても、人々が改善した状況に慣れてしまったり、そもそも希望する水準が高すぎたり、他の人々との相対的な関係が同じだと感じたりすると、幸福度は高まらないのである。
私から見ると、「2024年の満足度は2023年に比べて、0.1ポイント高まった」という議論をするよりは、「厚生労働省の毎月勤労調査によると、2024年の賃金上昇率は2.8%と近年にない高い上昇となった。特にパート就業者の賃金は3.9%も上昇した」という議論の方が客観的で明確な議論につながるように思われる。
「幸福度・満足度の調査・分析は重要ではあるが、経済政策のベースとしてはあまり評価できない」というのが現時点での私の結論である。
幸福度について考える(下)
2025.05.15