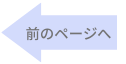著者
大正大学地域創生学部 地域創生学科 助教
天野浩史
実際、前年度まで受け身がちだった学生たちは、「直売所の調査をもっとやりたい」、「食を通じた活動をしたい」、「スポーツプロモーションを専門にしているから、健康やスポーツに関することを探究したい」などのテーマを掲げ、自発的・主体的に行動するようになりました。また、自分たちでフィールドでの時間の使い方を決める選択肢もつくり、その使い方をコーディネーター、理事長がサポートするという時間を広げることで、「自分たちが主人公となって行うフィールドワーク」という認識が強くなっていったようです。学生からも「自分たちが動かないと時間だけが過ぎていく」という感想や、「大学に戻ったらもっと調べてみたい」というフィールドと大学を接続させる行動目標を聴くことができました。
地域人材との信頼形成・関係醸成
もう一つの要因は、カウンターパートとなる地域住民・受入団体と学生との関係構築です。具体的に言えば、学生と受入団体(ここではA氏)との間の信頼形成・関係醸成です。とうもんの里におけるフィールドワークでは、必ず1年次に学生と理事長の個別面談が行われ、お互いを理解しながら、学生が描くやってみたいことや探究したいことを深ぼっていく時間を設けています。例えば、「私は食に関する活動をとうもんでやってみたい」と言っても、それを口にする学生自身が、そのテーマに半信半疑な部分があったり、本当にそれがやりたいことなのか?という不安も抱いていることは少なくありません。そんなときに「どうしてそれをやろうと思ったの?」、「私だったら、こう思うかな」と、A氏が問いを投げかけたり、自分の考えを語っていく中で、学生自身もそれを自分がテーマとして掲げた意味を再構築していきます。学生が使う言葉の意味を紐解きながら、A氏自身の経験知を元にしながら新しい意味を共創していく、そんな対話が個別面談の中では行われ、その過程を通じて、学生もA氏もお互いの関係性を深めてきました。
実際に、フィールドワーク終了後、卒業後もA氏の元を訪れては近況報告をしたり、悩みごとを相談する学生もいます。その話を聴くと、「フィールドワークの受け入れをする地域人材」を超えた「信じられる大人・パートナー」という関係性の土台には、こういった面と向かった対話の時間が大きな意味を成していたのではないかと感じます。

留学後、卒業後も自分のこれからやりたいことについて相談しに訪問
ここまでの話を聴き、フィールド教育に関わる方なら「こういったフィールドワークは受入側の負担が大きすぎるのではないか?」という懸念を抱くかもしれません。確かに、こういった学生の探究したいテーマに合わせて地域の人材・資源を発掘・コーディネートすることや、学生との深いコミュニケーション機会を設けることは、労力・時間ともに大変さもあります。しかし、地域・受入側にとって、自団体の都合でのコーディネートではなく、学生という新たな人材が掲げたテーマを起点にコーディネートすることは、地域人材との関係のつむぎ直しになったり、新たな人材や地域資源を取り入れることに繋がっていくなど、新たな社会関係資本の形成や地域資源の再認識という効果も期待されます。重要なのは、負担を軽減することではなく(もちろん業務上の負担を軽減することは前提としつつ)、フィールドワークコーディネーターが「フィールド教育を機会にして受入団体にどのような価値を創造できるか、どのような変化を生み出せるか」という戦略的視点も持ちながら、プログラム開発を進めることであり、そのためのコーディネートスキルの標準化と養成が今後の課題ではないでしょうか。この点も今後の研究課題の一つとして考えていきたいと思います。
こういったフィールド環境での「自身の関心にもとづいた主体的な学び」と、それを進めていく中で構築される「信頼できる大人との関係性」が相互に交差しながら、より深い学びと信頼が生まれ、学生自身の自己形成にポジティブな効果を生み出しているのではないか。とうもんの里におけるフィールドワークコーディネートから、そんな仮説を抱くようになりました。同時に、それはフィールドにおける偶発性を前提にしながらも、どこまでデザインが可能なのか…暗黙知的に処理されてしまいがちな領域でありますが、だからこそ、具体的なケースを紐解き、フィールドでのプログラム実践も行いながら、学びの支援論・コーディネート論を構想していきたいと思います。